沼津宿
| ・ | 黄瀬川を越えて |
| ・ | 黒瀬の渡し |
| ・ | 沼津宿から |
| ・ | 浮島沼へ |
| ・ | 原宿にて |
| ・ | 沼津城とその周辺 |
| ・ | 沼津の史跡と年表 |
| ・ | 街道の様子 |
| ・ | 庶民の旅 |
| ・ | 浮世絵コレクション |
| ・ | 絵草紙ほか |
| ・ | 小道具 |
| ・ | 関連リンク |
| ・ | |
| ・ | |
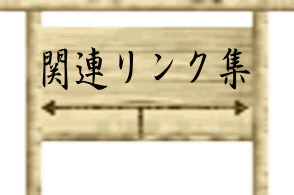 |
| 参考図書 | 東海道五十三次沼津宿を作成するにあたり参考にした図書やリンクサイトなどを紹介します。 | ||
< 沼津市関係> |
|||
 |
沼津市役所のページです。 1-24-09 |
||
| まさに沼津を紹介するページです。 | |||
 |
沼津市三枚橋町にあり、駐車場も整っており、利用しやすい図書館です。いつも大勢の市民が訪れ、あらゆる年齢層の人たちから親しまれている施設です。1-24-09 |
||
| 沼津医師会のページです。 夜間救急や、日曜当番医などが分かります。 |
|||
| 沼津市内にある新聞社。地域の情報を丁寧に教えてくれる。市民にとって不可欠な新聞社。 | |||
 寿太郎ミカンの原木 寿太郎ミカンの原木 |
沼津市西浦地区で生産されている、とてもおいしいミカン寿太郎は昭和50年に山田寿太郎さんが青島温州ミカンの変異枝を発見し育てたもので、その原木が今も2種類のミカンを実らせている。 | ||
| 沼津兵学校 | 明治2年に旧徳川家によって開設された沼津兵学校について解説。 | ||
 |
沼津信用金庫本店横にあるストリートギャラリーです。 月毎に変わるようですが、何時でも歩きながら素晴らしい美術品を楽しめます。 |
||
| 多数の短歌を詠んだ、若山牧水は晩年を沼津で過ごしました。牧水の作品が多数展示されている、静かなたたずまいの記念館です。 | |||
 牧水と千本松原 牧水と千本松原 |
沼津千本松原をこよなく愛した牧水は、松原に接した所に居を構えていた。松原の一部伐採計画に反対したときに書いた「沼津千本松原」と題する素晴らしい文章を紹介している。 | ||
| 沼津市木瀬川にある潮音寺の本尊・亀鶴観世音菩薩について解説。 | |||
 黄瀬川の砂 黄瀬川の砂 |
平塚市博物館のページです。黄瀬川の源流は箱根乙女峠で、愛鷹火山と箱根火山の間を流れる砂礫の多い川のようです。しかし沼津の海岸線を形成する砂浜の砂は富士川の砂だそうで、〜浮島沼へ〜で考察したように私の考えを証明してくれている。 | ||
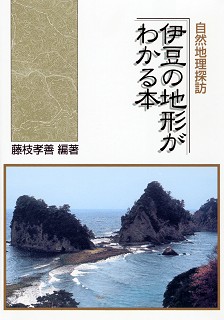 |
「伊豆の地形が わかる本」 沼津高専の先生が書いた本です。浮島沼についても記載があります。 | ||
| 香貫山に登った人の記録です。驚く事に香貫山には頂上付近に湧き水が出ているのです。これはきっと富士山からの湧き水だと思うのですが・・・。最近はここに蛇口が付けられているようです。 | |||
 沼津アルプス 沼津アルプス |
沼津アルプス知る人ぞ知る名山。香貫山から横山、徳倉山、志下山、鷲頭山、大平山へと続く低いけど歩き応えのある山並。富士山やら駿河湾やら、展望は天下一品。 | ||
 国境・境川 国境・境川 |
三島市と清水町の境を流れる境川(北斎が沼津の入り口として描いた千貫樋の下を流れている)は、伊豆の国と駿河の国を分けた国境の川だった。市街地にある緑地・水辺として保存活動がさかん。 | ||
| 沼津市立大岡小学校のホームページです 学校から東西南北の方向へ調査・探検した記事が掲載されています。 |
|||
| 牧堰用水や東海道足柄路について触れている。 R−246近くの黄瀬川に架かっている寿橋についての知見は興味深い。 |
|||
<美術館など> |
|||
 東海道広重美術館 東海道広重美術館 |
静岡市清水区油井にある歌川広重の版画を取り揃えた美術館です。とても素晴らしい作品が月替わりに展示され、広重の好きな方には必見です。1-24-09 | ||
| 収蔵品多く、検索システムがすばらしい。 | |||
| 浮世絵の豊富な検索があり、目を見張ります。 | |||
| 多数の浮世絵コレクションがあります。 | |||
| 美しい浮世絵がそろっています。 | |||
 |
タバコと塩の説明が良い。駿河湾は古くから塩の生産が盛んだったので興味深く拝見できた。 浮世絵の資料も豊富だ。 |
||
 |
三島市にある美術館。佐野隆一氏のコレクションが寄贈されて作られている。多彩な収蔵品で、幅広い展示内容を誇っている。広い庭園も見事だ。 | ||
| 駿東郡長泉町にあるベルナー・ビュッフェ専門の美術館です。 すぐ隣に井上靖文学館が併設されている。 |
|||
| 浜松市美術館のページです。収蔵品から浮世絵に入ると、末広五十三次が見られます。 | |||
<東海道の地域> |
|||
| 歴史研究所のページです。 静岡県を時代地図をもとに紹介。 |
|||
| 三島の名所・旧跡 | 三島市のページです。沢山の名所・旧跡を紹介しています。 | ||
| 三島宿 | 三島市のページです。三島宿の史跡を紹介しています。 | ||
|
|
|||
| 本宿の歴史を紹介。東海道足柄路や本宿用水、牧堰用水について説明されている。 | |||
 牛が淵 牛が淵 |
鮎壷の滝の少し上流にある景勝地。北条方の長久保城主、水野治郎右衛門の娘(萩姫)が武田の攻勢で落城の折、牛車もろとも身を投げたとされる。 | ||
 |
沼津市の隣にある、駿東郡清水町観光協会のページ。清水町の史跡を紹介している。千貫樋も駿豆電気鉄道軌道線跡と共に写真に写っている。 | ||
 |
長崎大学付属図書館の 古写真を紹介したページです。 浮島沼の様子がよく分かります。 |
||
| 凝視されたし左富士。富士市吉原にある左富士を紹介。 | |||
| 掛川宿、日坂宿、金谷宿について紹介しています。 | |||
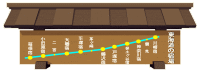 |
国土交通省横浜国道事務所のページです。神奈川県の宿場町を全て、今昔を丁寧に説明しています。街道の様子などとても参考になります。 | ||
 |
品川宿を様々な角度から紹介されており、さすがは品川と言う感じです。驚いた事に歩いているのは東海道だけでなく、様々な街道を紹介されています。 | ||
| 。 | |||
| 小田原市に関する浮世絵の紹介と、その解説が書かれています。沼津市とも関わりのある、曽我兄弟の浮世絵も多数解説されています。 | |||
 東海道47番目の宿場町 関宿散策 |
ぬいぬいさんの旅行ブログです。関宿を写真で紹介しています。見るだけで関宿に行ったみたいな気分になります。 | ||
| 横浜市のページです。東海道保土ヶ谷宿を紹介しています。 | |||
 |
横浜市保土ヶ谷区にある神明社のページです。保土ヶ谷を初めとする東海道の松並木についての考察など。 保土ヶ谷の浮世絵集があります。広重の保永堂版の人物アッフ像゚も魅力的です。 |
||
 |
桑名宿の七里の渡跡を紹介している桑名市のページ。周辺地図による史跡紹介も参考になります。 | ||
| 草津本陣遺構を紹介するサイト。 | |||
| 二川本陣遺構を紹介するサイト。 | |||
| 足柄峠・足柄路について解説。 | |||
| 玉川大学のHP.足柄古道を紹介。 | |||
| 富士川の戦い | 鎌倉幕府について解説。 | ||
<浮世絵を紹介> |
|||
 浮世絵文献資料館 浮世絵文献資料館 |
加藤好夫氏の編集・制作による資料が閲覧できます。多数の浮世絵師の文献検索が可能です。 | ||
| 額田隼人さんの浮世絵詩集です。素晴らしい浮世絵がズラリ勢揃いしています。浮世絵に興味のある方必見です。 | |||
| 大阪市難波にある上方浮世絵館のページです。上方浮世絵を展示解説しています。 | |||
| 広重、北斎、三代豊国、歌麿、国芳などの描いた江ノ島の浮世絵が多数。 古写真、古絵葉書、その他江の島についての全てが説明されている。 |
|||
| 保永堂の後摺り | 伊藤三平さんのページ.保永堂版、三島・朝霧について詳しく解説しています。 | ||
<東海道ウォーク> |
|||
  |
各宿場を丁寧に紹介しています。東海道、五街道だけでなく、脇往還にいたるまで網羅されています。すごいです! 1-24-09 |
||
| 東海道、中山道だけでなく長年にわたりご夫婦で、あちこちの街道や山歩きを楽しんでいらっしゃるようです。岡崎の方でしょうか、ほとんどが日帰りだと言うのもすごいですね。 | |||
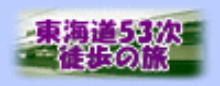 |
東海道ウォーキングのページです。宿場の様子が良くわかります。 |
||
| 東海道の様子を写真で紹介。とても分かりやすい。中山道も踏破されており、その他多彩な内容で楽しいページ構成だ。 | |||
| わくらばに 十二 | 松本あずささんの、東海道の街めぐりのページです。 沼津藩領傍示石が紹介されています。 |
||
<街道の様子> |
|||
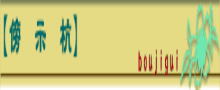 |
傍示杭や高札場、街道の様子が丁寧に説明されています。神奈川県の宿場町を紹介している国土交通省のページです。 1-24-09 |
||
 池鯉鮒宿の松並木 池鯉鮒宿の松並木 |
知立市の加藤哲久さんのページです。池鯉鮒宿の松並木や一里塚、その他の名所旧跡を紹介しています。 | ||
| 東海道一里塚(神奈川県) | 東海道の一里塚を詳しく紹介しています。 | ||
| 東海道の全ての一里塚が紹介されています。「従是西沼津領」の傍示石も写されています。 | |||
| 東海道の石造道標 | 山下宏明さんのページで、東海道のみならず中山道その他多くの街道の道標を紹介。「諸人往来みちしるべ」の部分。 | ||
 国境 国境 |
権太坂を過ぎて保土ヶ谷区から戸塚区に入ったところに境木地蔵尊がある。ここは武蔵の国と相模の国の境だった。 | ||
<江戸時代の制度> |
|||
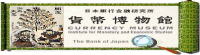 |
日本銀行のページです。お金について、全て分かります。 | ||
| 飛脚問屋の世界 | 飛脚問屋で使用した印鑑や古文書を紹介している。 | ||
| 江戸時代の通信・飛脚について資料を交え解説。 | |||
| 赤穂への早駕籠 うえやまさんのページです。 | |||
<江戸庶民> |
|||
| 江戸時代の制度や庶民の暮らしについて、分かりやすく教えてくれる。 | |||
 |
虚無僧は普化宗の徒で、出家者として全国を行脚していた。しかし僧ではなく、剃髪はしていなかった。虚無僧になるには武士である事が条件であったようだ。 | ||
| 江戸庶民の生活や城下町、江戸城の様子などを紹介。 | |||
| <その他 > | |||
| 鍵屋の辻の決闘(1634) | 荒木又衛門の36人切りで有名な、 三大敵討のひとつを解説。 | ||
戻る